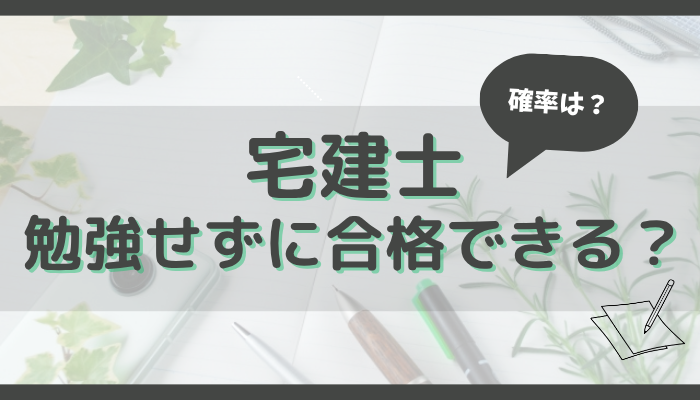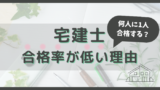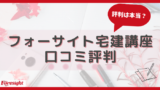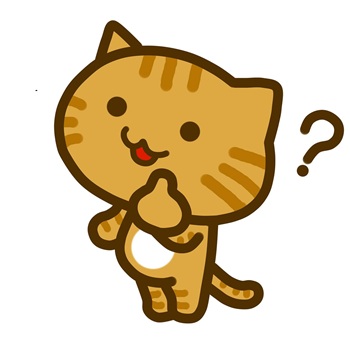
宅建って、勉強せずに合格できる?
この質問をよくいただくので、筆者なりの見解を記事にします。

●この記事を書いた人
サイト管理人:宅建士
不動産会社に勤務してた人。独学で宅建合格(300時間ぐらい勉強した)
自分の周りに宅建の勉強法で悩む人が多いので、このサイトを秘伝書として立ち上げました。
宅建に勉強せずに合格できる?【結論:ほぼ無理】
宅建士試験に合格するには、一定の知識が必要です。 ノー勉で合格を勝ち取るのは、神がかり的な勘が働かない限り、まず無理と言わざるを得ません。
宅建試験は、毎年約20万人が受験し、合格率は15〜18%前後にとどまる国家資格。数字だけ見ても、勉強なしでの合格がどれほど難しいかは明らかです。
令和 6 年度宅地建物取引士資格試験結果
合格率 18.6%
出題範囲と難易度を考えると、勉強ゼロでの合格は非現実的
宅建士の試験では、
- 法律の知識(民法・宅建業法など)
- 税の知識
- 建築基準法
- 都市計画法
……など、幅広い分野の知識が問われ、単なる暗記だけでは太刀打ちできない内容が出題されます。
そのため、勉強せずに合格するには、かなり特殊な知識背景※があるか、まぐれ以外に方法はないと言えるでしょう。
※特殊な知識背景の例
| 特殊な知識背景 | 例 |
|---|---|
| 法学部出身 | 法律や行政の基礎的知識がある人 |
| 不動産業界での長年の実務経験 | 不動産販売や管理の実務で法律や契約の知識が身についている人 |
| 関連資格を取得している (マンション管理士など) | 不動産関連の知識をすでに身につけている人 |
| クイズ王、雑学王 | あらゆるジャンルの知識を広く持ち、宅建知識にも対応できる人 |
| 記憶力が異常に優れている | 暗記力に特化し、大量の情報を吸収できる人 |
宅建に勉強なしで合格する確率はどのくらい?

宅建に勉強なしで合格する確率は、ざっくり約 0.00000000255%ぐらい
(計算式にもよる)
宅建試験は4択のマークシート形式で50問出題され、1問1点。
合格するには、だいたい35点以上が必要です。
(注意:合格ラインは、毎年変わります)
すべての問題を当てずっぽうで解いた場合の確率
勉強せずに完全に運だけで、50問ある4択問題のうち35問以上を正解する確率は約 0.000000003%です。
P(X ≧ 35) = 1 − P(X ≦ 34)
= 1 − BinomCDF(n=50, p=0.25, k=34)
≒ 0.0000000000295
= 約0.000000003%
筆者は、計算問題がとても苦手なので、ツールで数字を出しています。間違ってたら申し訳ない。
ただ、体感的にも「勉強せずにあてずっぽうで50問の4択を解いたら、そりゃ当たらないよな」という感覚はあります。
実際、筆者の周りでノー勉で宅建を受けた人の点数は「7点だった」や「13点取れた」などの報告が多く、合格には程遠いレベルばかりです。
0.000000003%の現実的な意味
宝くじで1等に当たる確率は約1,000万分の1(0.00001%)といわれています。
宝くじで1等が当たる確率は?
1等が当たる確率は1,000万分の1です。
なので、宅建の4択50問をあてずっぽうで35問以上正解する確率(約0.000000003%)は、「宝くじの1等よりもはるかに低い確率になります。
| 比較対象 | 当たる確率 |
|---|---|
| 宝くじ1等 | 約0.00001% |
| 宅建50問中35問以上を4択で適当に正解 | 約0.000000003% |
不動産会社勤務なら勉強せずに宅建合格できる?

不動産会社に勤めているから試験もいけるのでは?
こうも思われがちですが、不動産業に携わっていても、宅建をノー勉で受かるのは難しいです。
実務経験と試験範囲のズレ
不動産業務の現場では、イヤでも宅建業法や契約実務に触れます。
しかし、宅建試験では実務で触れない法令や、権利関係のややこしい知識、宅建業の免許の知識なども問われます。
不動産業の実務経験はアドバンテージにはなりますが、試験範囲すべてをカバーするには不十分です。
5問免除制度でも45問は残る
宅地建物取引業に従事していれば、講習を受けることで「5問免除制度」が利用できます。
「50問中の5問分が、問答無用で正解扱い」になるため、一般試験と比べて格段に有利ではあります……が。
それでも結局、残る45問は自力で正解を導かなければならず、勉強なしで乗り切るのはキビしいです。
法学部出身なら、勉強せずに合格できる?
法学部で法律の知識を学んでいても、やはりノー勉での宅建合格は難しいです。
ただし、民法・権利関係の分野でロケットスタートを切れるため、法律まわりは有利ではあります。
民法の理解は大きなアドバンテージになる
宅建の民法は、基本的な条文や考え方を問う問題が中心です。法学部で既に履修している人であれば、基礎知識の蓄積があり、思考パターンも試験にマッチしています。
実際、民法を得点源にできる法学部出身者は多く、これは明確なアドバンテージです。
ただし、民法だけで合格点には届かない
民法の出題は全50問中14問程度しかありません。
残る36問は、宅建業法・法令上の制限・税金など、不動産実務に寄せた知識が求められます。
これらは法学部では通常扱わない分野のため、まったく勉強しないで解ける問題ではありません。
「宅建に勉強せずに受かった!」の報告は本当?
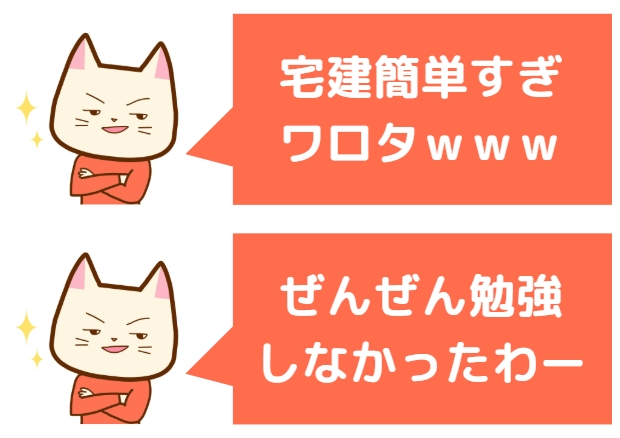
X(旧Twitter)やYouTubeなどで、「勉強ほとんどしなかったけど宅建受かりました!」という投稿を見かけた経験がある人もいるかもしれません。
これについては完全に嘘とは限りませんが、真に受けすぎない方が安全です。
「勉強していない」の基準が違うだけ
こうした発言の多くは、よく見てみると以下のような事情があります。
- 法学部出身で民法に強い
- 不動産業界で働いており、宅建業法や法令上の制限に詳しい
- 過去に一度落ちていて、今回は復習のみ行った
- 直前に1~2週間だけ詰め込んだケースを「勉強してない」と表現している
つまり、「本人の感覚としては勉強していないけど、実際は下地がしっかりある」といったケースが多いです。
筆者の実体験:不動産会社勤務でも、ノー勉で合格した人はいない
筆者は不動産会社に勤めており、毎年複数のスタッフが宅建試験に挑戦しています。
業務で宅建業法に触れているため有利な面もありますが、それでも全く勉強せずに合格した人は見たことがありません。
勤務歴10年超で業法に詳しいスタッフも、民法や法令上の制限の部分で苦戦しています。
逆に、新人のスタッフさん(宅建初学者)でもコツコツ勉強して合格した人もおり、やはり努力の量と結果はある程度比例すると感じます。
「勉強してない」の定義が人によって違う
「勉強せずに合格しました」と言っている人の中には、勉強の定義そのものが違うケースもあります。
たとえば……
- 「机に向かって何時間もゴリゴリ勉強する」のが勉強だと思っている人
→実際は、通勤時間にスマホで過去問を解いたり、音声講義を聞いてコツコツ覚えていた - 「資格試験=不眠不休で努力してこそ!」という価値観の人
→宅建の勉強が思ったより楽に感じたため、「これは勉強と呼ぶほどじゃない」と判断している
こういった人たちは、自分としては努力したつもりはないけれど、他の人から見ればかなりやっている状態です。
つまり、勉強してないという言葉をそのまま受け取ると、実態とズレる可能性が高く、危険です。
勉強せずに宅建を受けるのは、受験料と交通費のムダ
勉強せずに宅建資格に挑戦するのは、お金のムダです。
受験料と時間を浪費するだけで、得られるものはほとんどありません。
宅建試験の受験料は8,200円と、財布にかなりのダメージを与えてくる金額。加えて、受験会場までの交通費などの実費もかかります。
勉強せずに受験しても合格の可能性は極めて低いため、これらの費用が完全に無駄になってしまいます。
8,200円あったら美味しいものがたくさん食べられるので、ノー勉での宅建受験は、お金をドブに捨てるようなものです。
勉強時間を最小限に抑えて宅建合格を目指す方法ならある
まったく勉強せずに宅建に合格するのは難しいですが、学習時間を最小限で済ませて合格する方法なら、あるにはあります。
以下、少しお話します。
頻出問題に絞った宅建教材で効率的に学習
宅建の教材選びでミスらなければ、学習時間を大幅に短縮できます。
具体的には、頻出問題に絞ってシンプルに、「出る箇所だけ」を解説してくれる教材を選べば、学習効率が高まります。
フォーサイトの宅建講座は、 出題範囲のすべてを網羅するのではなく、出るところに集中して最短でゴールにたどり着く設計なので、時間がない社会人や主婦層からも人気です。

実際、筆者の周りでも、この講座を活用して勉強時間を大幅に短縮し、合格したスタッフがいます。
頻出科目に絞る
頻出科目=宅建業法です。
宅建業法は得点源となりやすく、比較的覚えやすいため、まずここを重点的に対策しましょう。
過去問を徹底的に繰り返す
過去5年分を3回以上解き、出題パターンを体感的に覚えてしまいましょう。
選択肢の傾向やひっかけポイントを体得できるため、最短学習に過去問は必須です。
スキマ時間の活用
通勤中や昼休みなどのちょっとした時間を活用して、暗記項目をマスターしていきます。
スキマ時間を利用すれば、まとまった勉強時間が取れなくても合格を狙えます。
宅建:参照サイト