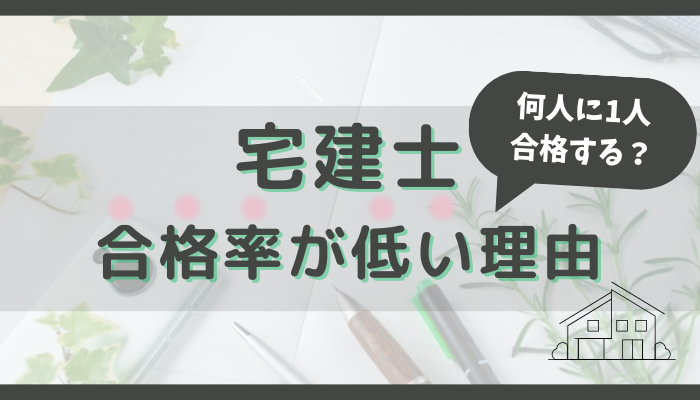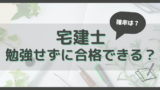宅建試験の合格率は例年10%台で低い水準です。受験者の約5~6人に1人しか合格できていません。
では、なぜこれほど合格率が低いのでしょうか?
宅建の合格率が低い背景には、試験そのものの特性や受験者層の特徴が影響しています。この記事では、宅建試験の合格率が低い理由を紐解いてみます。

●この記事を書いた人
サイト管理人:宅建士
不動産会社に勤務してた人。独学で宅建を学び合格できました。学習時間は300時間ほど(うろ覚え)。
自分の周りに宅建の勉強法で悩む人が多いので、このサイトを秘伝書として立ち上げました。
筆者のまわりは、フォーサイトの宅建講座を受講しているスタッフが多いです。
「シンプルなテキストで使いやすい」
「余計な知識を覚えなくて済む」
「最短距離で合格を目指せる」
……と好評です。
実際に合格した人もいるので、自信を持っておすすめしています!
\合格率は全国平均の4.26倍/
宅建の合格率が低い理由
宅建の合格率は、例年15~20%程度。
合格者は5~6人に1人の割合です。
宅建の合格率が低い理由で考えられるのは、次の要素です。
- 不動産会社の人が、ノー勉で受験するから
- 試験が年1回のみの一発勝負だから
- 試験本番のプレッシャーにやられた
- 法改正を落とした層が多かったから
- 試験範囲が広すぎて、合格率が低い
- 専門用語が多いので、合格率が低い
- ひっかけ問題があり、合格率が低い
- 合格点は相対評価で決まるため、合格率が低い
順に、くわしく見てみましょう!
宅建の合格率が低い理由①
不動産会社の社員が、ノー勉でイヤイヤ受験しているので、合格率が低い
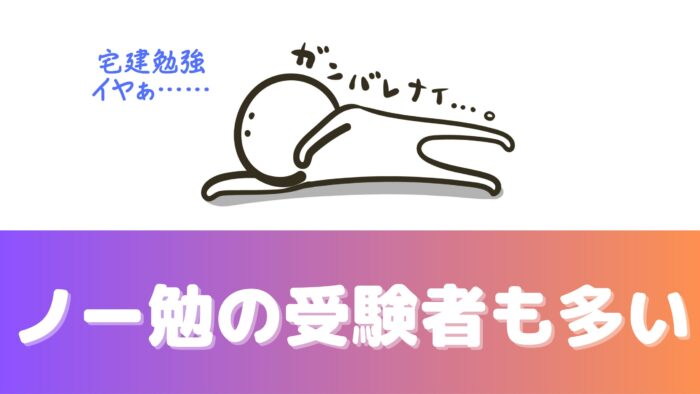
不動産会社では業務の性質上、社員に宅建資格の取得を義務付ける企業も多いです。
不動産適正取引推進機構が発表している過去の受験データでは、宅建試験の職業別受験者は不動産業が30.6%とダントツでトップでした。
職業別 不動産業30.6% 金融業9.0% 建設業8.9% 他業種28.6% 構成比 学生11.4% その他11.5%(本年度より「主婦」はその他に含んでいる。)
しかし、必ずしも不動産会社のスタッフ全員が強い意欲を持って受験に望んでいるわけではありません。
宅建の試験勉強に身が入らないまま受験日を迎える人も、かなりいます。
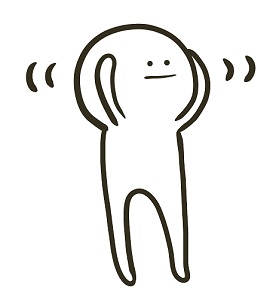
上司に怒られるから、とりあえず受験している感じ。
筆者の体感上、不動産会社に勤めていて、しぶしぶ宅建試験に臨んでいる人は、めちゃくちゃ多いです。
なんなら、試験に申込だけして「どうせ落ちるから」と、試験日に会場にすら行かない人もよく見ます。
このような「イヤイヤ試験を受けている層」が、宅建士の合格率を押し下げる要因となっています。
宅建の合格率が低い理由②
試験が年1回のみの一発勝負なので、合格率が低い
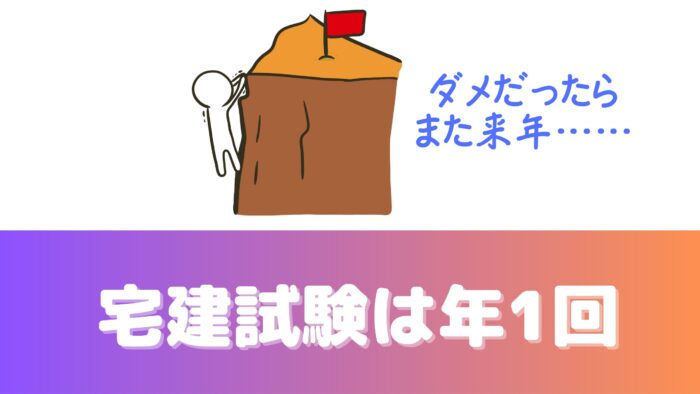
宅建試験は年に1度しか実施されないため、万全の準備が整わないまま挑むと不合格となり、次回の受験まで1年間待たなければなりません。
ケアレスミスだけでなく、試験会場に遅刻した、当日にコンディション不良で頭が回らなかった――
このような要因でも試験に失敗してしまうので、たとえ合格レベルの宅建知識を持っていたとしても、外敵要素により落ちてしまう可能性があります。
宅建の合格率が低い理由③
試験本番の緊張やプレッシャーが影響し、合格率が低い
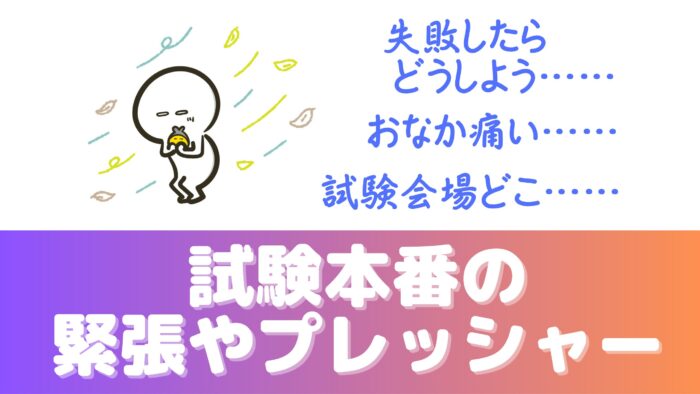
試験当日の環境やプレッシャーで実力を発揮できない受験者もいます。
特に初めて受験する人や、時間配分が苦手な人は、本番で予想以上に苦戦するケースが考えられます。
宅建の合格率が低い理由④
法改正を学ばずに試験を受ける層がいるので、合格率が低い
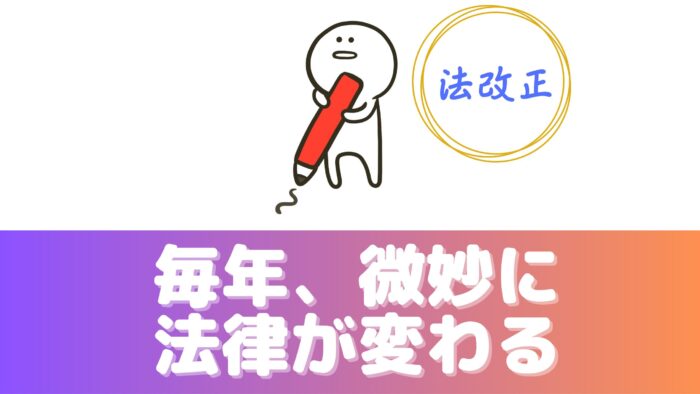
宅建試験は法改正によって、毎年、出題傾向が微妙に変化します。
古いテキストを使っていた場合などで、最新の宅建業法、法改正に対応できていない場合は、宅建試験のハードルが上がるため、合格率に影響します。
宅建の合格率が低い理由⑤
試験範囲が広すぎるので、合格率が低い
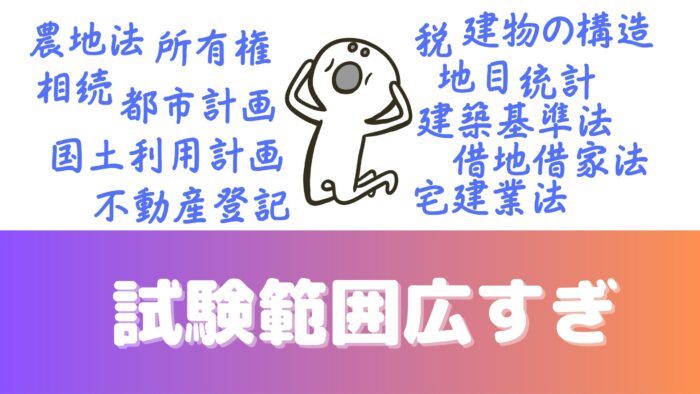
宅建試験では、不動産取引に関する幅広い知識が問われます。出題範囲は以下のように多岐にわたります。
| 宅建業法 | 不動産取引の基本ルールや業界の規定 |
| 民法、権利関係 | 法律の知識 |
| 法令上の制限 | 法規制や建築基準法に関する細かい知識 |
| 税金・その他 | 不動産に関連する税金や統計知識 |
単純に、試験範囲が広すぎるため、出る箇所をヤマかけしていた場合や、広く浅く学習して、知識が中途半端になっていた場合は、合格率を押し下げる要因となります。
宅建の合格率が低い理由⑥
専門用語が多くて難しいので、合格率が低い
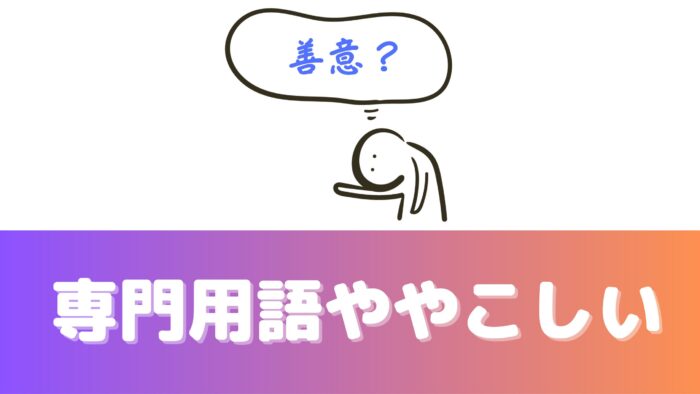
宅建試験には、ふつうに生きている上では耳にしない単語も多く登場します。
- 善意無過失
- 対抗
- 抵当権
- 非嫡出子
- 善管注意義務
- 市街化調整区域
- 建ぺい率……など
法律関連の用語や、都市計画に関する用語、宅建業に関する用語などが多く出てくるため、法律や不動産取引の知識に不慣れな受験者には難解に感じられる内容が多く、合格率に影響します。
宅建の合格率が低い理由⑦
ひっかけ問題がある
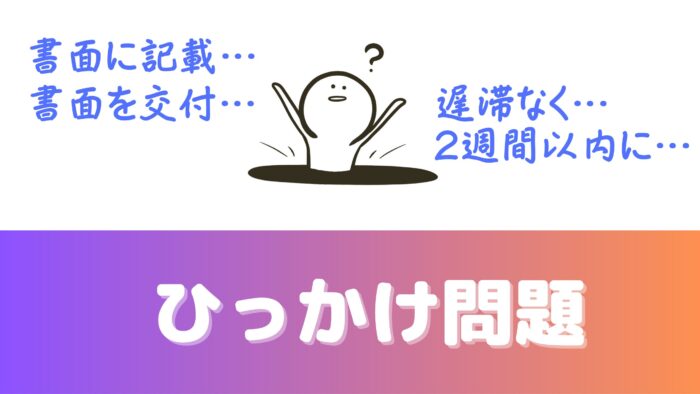
宅建試験では、問題文や選択肢に注意深く目を通さないと、ひっかけ問題に引っかかってしまいます。
例:都市計画の問題だと……
- 100㎡以上の建物に対して、規制が適用される
- 100㎡以下の建物に対して、規制が適用される
- 100㎡未満の建物に対して、規制が適用される
- 100㎡超えの建物に対して、規制が適用される
一見、内容が似ているように見えますが、法律上では「以上」と「以下」が重要な違いを生みます。
ただでさえ長ったらしい選択肢の中に、「細かい罠」が仕掛けられているので腹立たしいです。
このような表現の微妙な違いを見逃すと、誤った選択肢を選んでしまいます。
宅建の合格率が低い理由⑧
合格点は「相対評価」で決まるため、合格率が低い
宅建試験は50問出題され、満点は50点です。
ただ、「35点取れば、必ず合格!」という線引きはありません。合格点は、毎年変動します。これは、宅建試験は相対評価で合格基準が決まるためです。
例:
今年の合格ラインが「成績上位の15%」に設定された場合
→得点が上位15%に入った受験者のみが合格
このため、試験が難しかった年は合格点が下がり、試験は簡単だった年は合格ラインが跳ね上がる感じになります。

このシステムにより、
合格点のボーダーラインをギリ超えられなかった層……
「1点足りなくて不合格になった」と悲しむ受験者が多く発生する……
宅建の合格するのは「何人に1人」?
宅建試験の合格率は、毎年15~20%程度。
およそ「5~6人の受験者のうち、1人」が宅建試験に合格している計算になります。
真剣に挑む人の合格率はもっと高い?
宅建試験の受験者の中には、「会社の指示で、なんとなく受験しているだけの層」「ただ、願書を出しただけの層」がいます。
実際に、不動産適正取引推進機構の統計には、次のようなデータもあります。
| 申込者数 | 301,336人 |
| 受験者数 | 241,436人 |
| 受験率 | 80.1% |
| 合格者数 | 44,992人 |
| 合格率 | 18.6% |
職業別 不動産業30.6% 金融業9.0% 建設業8.9% 他業種28.6% 構成比 学生11.4% その他11.5%
参考:https://www.retio.or.jp/exam/
宅建の申込には、8,200円以上のお金がかかりますが、申込をしただけで受験をしなかった人数が、およそ6万人弱、いるのは興味深いです。
このような「受験するだけ」「申し込んだだけ」の、真剣に宅建に向き合っていない層を除いて考えると、マジメに学習した人の合格率は、統計上の数字よりも高くなると推測されます。
宅建試験に落ちてしまう理由の多くは、準備不足や意欲の低さです。
逆に言えば、しっかりと準備をして挑めば、5~6人に1人の「合格者」に入ることは十分可能――というのが、私の見解です。

宅建は、本気で取り組めば合格できる!
宅建の独学におすすめの通信講座や教材は次の記事で紹介しているので、良ければ参考にしてくださいまし。
他資格と比較した宅建の合格率
ついでに、宅建試験の合格率を他の国家資格と比較してみましょう。
数値は、ざっくりした平均値です。
| 資格名 | 合格率 | 難易度(比較) |
|---|---|---|
| 司法試験予備試験 (弁護士) | 約3% | 非常に難しい |
| 社会保険労務士 | 約6%〜7% | やや難しい |
| 公認会計士 | 約7% | 難しい |
| 行政書士 | 約12% | 中程度 |
| 宅建 | 約15% | 中程度 |
こうして見てみると、宅建試験は国家資格の中でも、比較的「難関資格」としての位置づけではある、
しかし、真剣に取り組めば、合格に手が届く――と言えそうです。
宅建試験の基本情報
宅建試験(宅地建物取引士資格試験)は、不動産業界で働く上で必要不可欠な国家資格の一つ。
不動産取引の専門家として、法律や税務、契約に関する知識を証明するものとして位置づけられ、試験験は毎年10月に全国一斉で行われます。
| 出題形式 | 四肢択一 マークシート方式 |
| 試験時間 | 120分 |
| 出題数 | 50問 |
| 合格基準 | 毎年変動 31~36点が目安 |
| 合格率 | 例年15~20%程度 |
| 何人に一人? | 5~6人に1人が合格 |
| 試験日 | 年1回 (10月の第3日曜) |
宅建:参照サイト